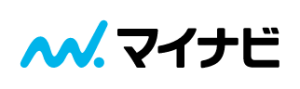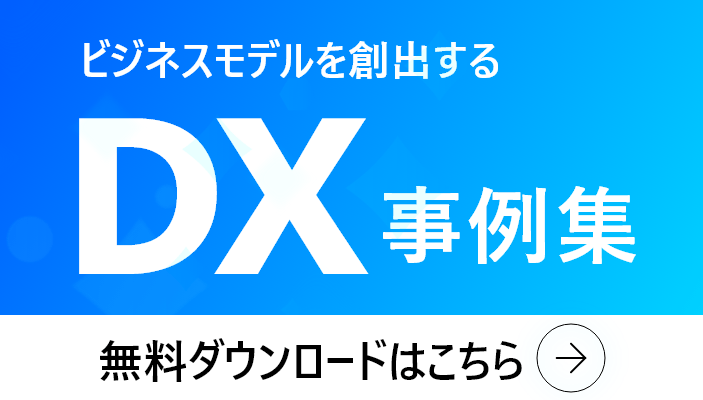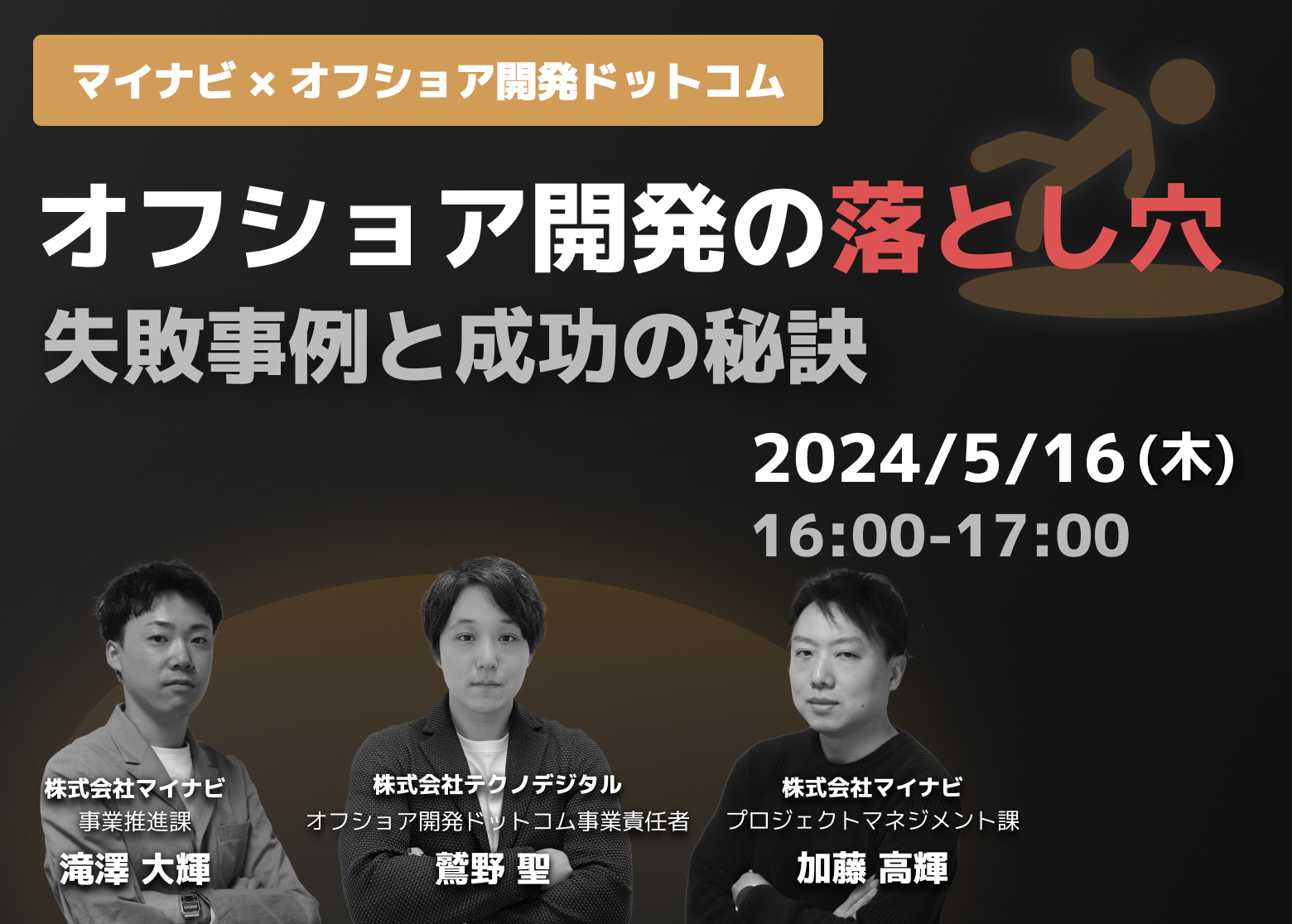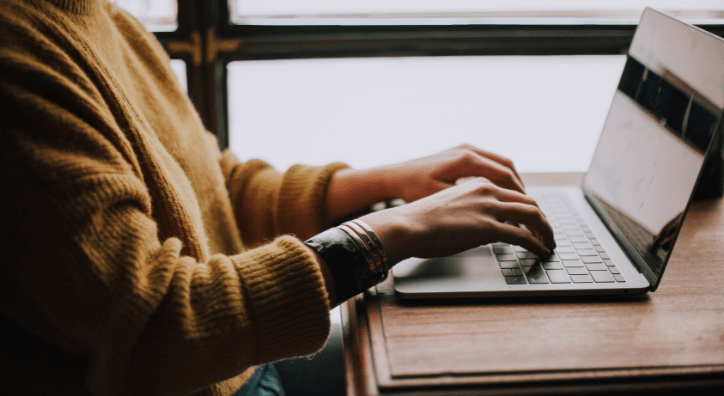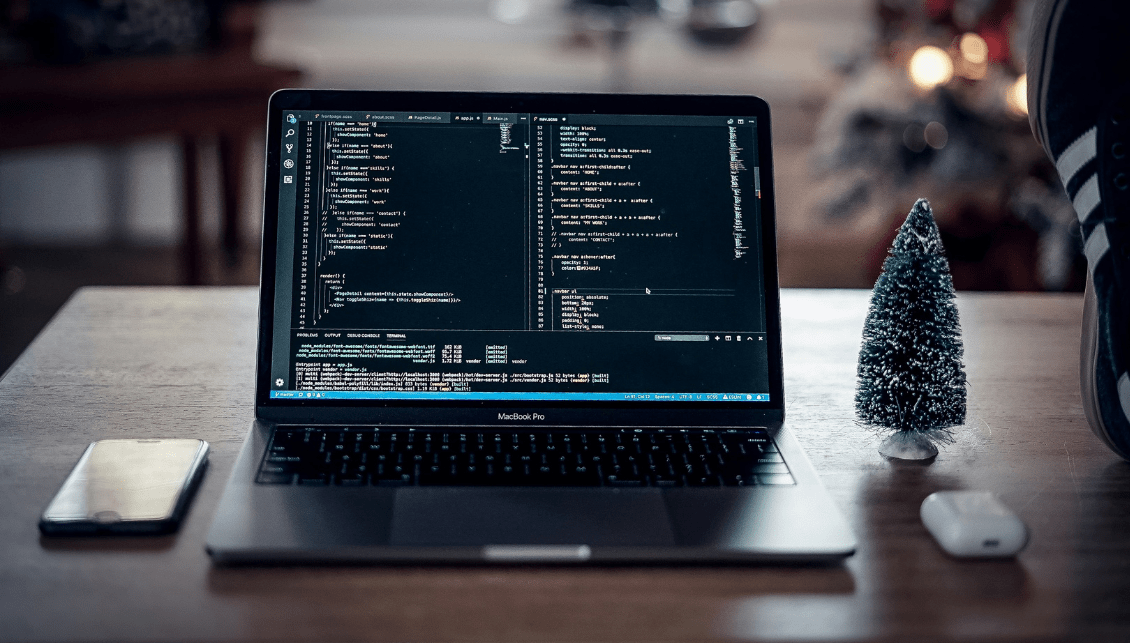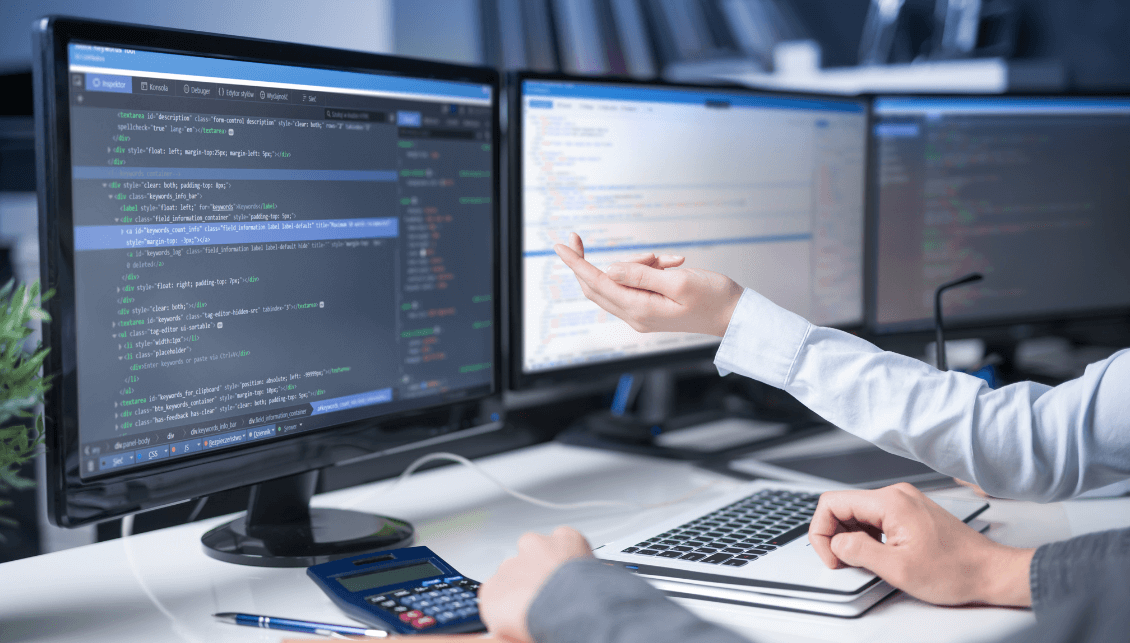システム開発における瑕疵担保責任と契約不適合責任は、システム開発の発注側とシステム開発側の双方にとって重要な法的概念です。
この記事では、システム開発における瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いや、それぞれに該当するケース、しないケースを事例とともに解説します。 システム開発を発注する際のスムーズな進行やリスク回避に役立てましょう。

INDEX 目次
瑕疵担保責任、契約不適合責任とは?
まずは、瑕疵担保責任、契約不適合責任それぞれの定義と違いを説明します。
瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任とは「売買契約において商品に瑕疵(欠陥)があった場合、売主がその責任を負う」という原則です。 民法第562条では、売主が買主に対して無瑕疵(欠陥がないこと)を保証すること、 万が一瑕疵があった場合、買主は売主に対して無償の修補、代物の交換、もしくは支払い金額の減額を求められると記載されています。
これをシステム開発に当てはめると、開発し納品されたシステムに欠陥が見つかった際、システム開発者がその修正を行なう責任があるといえます。 このため、システムの発注者が開発者に対して法的な責任を問うことがあります。
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
瑕疵担保責任は旧民法の概念で、2020年4月に施行された改正民法によって廃止されました。 この際、瑕疵担保責任の代わりに導入されたのが契約不適合責任です。 ここでは、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いを説明します。
責任を問うポイント:不具合の有無か、契約内容との違いか
瑕疵担保責任は「システム開発者が提供したシステムに、欠陥や不具合があった場合に発生する」とされていました。
一方、契約不適合責任は「契約の内容が、約束された品質や性能と異なる場合に発生する」とされています。 つまり、瑕疵担保責任は欠陥や不具合の存在に焦点を当てた責任であり、契約不適合責任は契約内容との不一致を取り扱う責任です。
責任の主体:システム開発者か、双方か
瑕疵担保責任は、一般的にシステム開発者に課される責任で、発注者が損害賠償を求めることができます。
契約不適合責任は、システムの発注者が主張することはできますが、契約の当事者間の責任を取り扱います。
システム発注者の証明責任:不具合の有無か、契約内容との違いか
瑕疵担保責任では、開発したシステムの発注者が「欠陥や不具合の存在を証明する責任」があります。
契約不適合責任でも、システム開発の発注者に証明責任はありますが、この場合は「契約条件に合致しないことを証明する責任」があります。 契約書や関連法規に沿って裁定が行なわれるため、契約を締結する段階で、契約書の作成や確認についてに専門家の助言を受けると良いでしょう。
契約不適合責任に関するトラブル事例
契約不適合責任に関連するトラブル事例をご紹介しましょう。
販売管理システムの開発を依頼し、納品後、システムに不具合が発生した。 システム開発側が不具合を認めず補修を拒否したところ、発注側が、開発にかかった請負代金の支払いを拒否。 これにより開発側が訴訟を起こし、発注側に対して請負代金を要求した。 一方、発注側は反訴し、システムの不具合を理由とする請負契約の解除と、前払金の返還を求めた。
- システム開発会社→発注者への本訴請求:請負代金(約1億1522万円)
- 発注者→システム開発会社への反訴請求:損害賠償(約1億3266万円)
| ポイント | 開発側の主張 | 発注側の主張 |
|---|---|---|
|
|
|
この事例の判決は、開発側の請求の棄却、および発注側の請求の一部認容です。 結果として、システムの開発側が発注者に対して前払金1143万円を返還し、同時に損害賠償金581万円を支払うことになりました。 今回の契約上は、重大な不具合に対して補修が行なわれなかったため、契約の解除に値するとされました。
契約不適合責任に該当する場合、しない場合
システム開発において契約不適合責任に該当する場合、しない場合の一般的な例をいくつか紹介します。
契約不適合責任に該当する場合
システム開発において契約不適合責任に該当するのは以下のような場合です。
- 機能の不足や不具合がある
- 納期が遅延する
- サポートや運用保守内容に不備がある
- セキュリティ要件が不足している
- 負荷テストやパフォーマンスが不足している
- 法的なコンプライアンスが不足している
機能の不足や不具合がある
開発されたシステムが、契約で定義された機能を満たしていない、またはバグやエラーが多数存在する場合、 契約不適合責任とみなされます。これには、約束されていた機能が実装されていない、正しく動作しない場合も含まれます。
納期が遅延する
プロジェクト進行が遅れ、契約に記載された納期を守れない場合も契約不適合責任に該当します。 システムの発注者が計画していたビジネスの計画に影響する場合もあるため、損害賠償の対象になる可能性があります。
サポートや運用保守内容に不備がある
システム開発の契約には、システムに対する一定期間のサポートや運用保守に関する規約が含まれることがあります。 契約に則したサービスが提供されない場合、契約不適合責任が発生する可能性があります。
セキュリティ要件が不足している
開発されたシステムが、契約で定められたセキュリティ基準や規格を満たしていない場合、 データ漏洩により顧客情報が危険にさらされるなど、システムの発注者に重大なリスクをもたらす可能性があるため、 契約不適合責任にあたる場合があります
負荷テストやパフォーマンスが不足している
開発したシステムに必要なデータ量などを処理できない場合などがあたります。 特に、開発したシステムがビジネスの重要な部分や業務を担う場合、 パフォーマンス不足は業務に深刻な影響を与える可能性があり、契約不適合責任になり得ます。
法的なコンプライアンスが不足している
開発したシステムやプロジェクトそのものが、特定の業界規格や法的な要件を遵守していない場合、 契約不適合責任にあたる可能性があります。
契約不適合責任に該当しない場合
システム開発において契約不適合責任に該当しないのは以下のような場合です。
- 要求変更が管理されている
- リスクが事前に通知されている
- 外的要因による影響
- 発注者の協力不足
- 検証や承認が完了している
要求変更が管理されている
システムの発注者からの変更や追加要求に対して、 納期や費用、仕様などの変更が合意されている場合、契約不適合責任には該当しない可能性があります。
リスクが事前に通知されている
システムの開発者が、発注者に対して事前にリスクを明示したにも関わらず、 発注者が適切な対応をしなかったことにより問題が起こった場合は、契約不適合責任に該当しない場合があります。
外的要因による影響
自然災害、政府の規制、システムと連携している他社サービスの障害などの 外的要因によって開発プロジェクトの遅延や不具合が発生した場合は、一般的には 契約不適合責任には該当しません。
発注者の協力不足
システムの発注者から開発者に対して、契約で取り決めたリソースや情報が十分に提供されず、 開発が難しくなることがあります。このような場合も、契約不適合責任に該当しないケースが多いです。
検証や承認が完了している
開発されたシステムを発注者が承認済の場合、承認後に発覚した問題点を 契約不適合責任として問うのは難しい可能性があります。
準委任契約や検収後の場合は?
準委任契約や検収後の場合も、契約で取り決めた内容によって契約不適合責任の有無は異なります。 契約不適合責任の有無の分かれ目になり得るポイントを説明します。
準委任契約の場合:手段やプロセスに関する指示や条件を確認する
準委任契約では、システム開発者は約束された結果を達成する責任を持ちますが、 一般的には結果を達成する手段が自由とされ、システム開発における納品物などが確約されていないことが多いです。
このため、結果が達成されなかった場合、 特に契約に含まれている手段やプロセスに関する詳細な指示や条件が満たされていない場合は 契約不適合責任に該当する可能性があります。
検収後の場合:検収後の不具合に関する対応内容を確認する
開発したシステムの検収後に不具合が発見された場合の契約不適合責任は、 検収後の不具合に対する対応が、どのように取り決められていたかによって異なります。 不具合がシステムの開発者に起因する場合・もしくは発注者に起因する場合それぞれの費用負担や、 対応可能期間について、契約の締結時に明確にしておくことが大切です。
システム開発の契約書作成・確認のポイント
契約不適合責任に関するトラブルを防ぐためには、 システム開発の契約締結の際、発注者と開発者の双方がしっかりとコミュニケーションを取り、 契約書において適切な合意形成をすることが大切です。
ここでは、システムの開発者と発注者それぞれにおいて、契約書を作成・確認する際のポイントを解説します。
システムの開発者が契約書を作成する際のポイント
システム開発の開発者が契約書を作成する際は、以下のような内容を明確に記載することが大切です。
- 開発するシステムの要件や仕様
- システムの納期、納品物、遅延時のペナルティ条件
- 要求変更が発生した場合の手続きや費用への影響
- システムの保証期間、その後の保守体制・料金
- システムに発生した不具合の定義、優先度、対応期限
システムの発注者が契約書を確認する際のポイント
システム開発の発注者が契約書を確認する際は、以下のようなポイントに気を付けましょう。
- 開発内容:開発の目的を満たし、開発範囲が必要な要件をカバーしているか
- 費用:市場価格と比較して妥当か
- リスク:トラブルや変更時にリスクを最小化する条項(例: 体制、ペナルティなど)が含まれているか
- セキュリティ:個人情報保護やデータのセキュリティに関して、遵守すべき法令や規範、責任分担が記述されているか
まとめ
この記事では、システム開発における瑕疵担保責任、契約不適合責任を解説しました。
下記に当記事のポイントをまとめておきます。
- 契約不適合責任は2020年4月に施行された改正民法で廃止され、代わりに契約不適合責任が導入された
- 契約不適合責任は、契約内容との不一致を取り扱う責任になっている
- 機能不足や不具合、納期の延期、保守内容に不備などがあった場合、契約不適合責任に該当する
- 準委任契約や検収後の場合、契約で取り決めた内容によって契約不適合責任の有無は異なる
- 契約不適合責任に関するトラブルを避けるには、契約書による適切な合意形成が必要
自社のシステム開発でトラブルが起きないよう、契約不適合責任に対する理解を深めましょう。
「どのように契約書を作成したらいいかわからない」という方は、ぜひ株式会社マイナビにご相談ください。
開発目的や予算をヒアリングさせていただき、最適なご提案をいたします。契約書のまとめ方や相場の情報といった相談だけでも大丈夫です。ぜひお気軽にご相談ください。

Recommended Materials
おすすめ資料