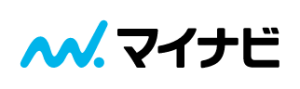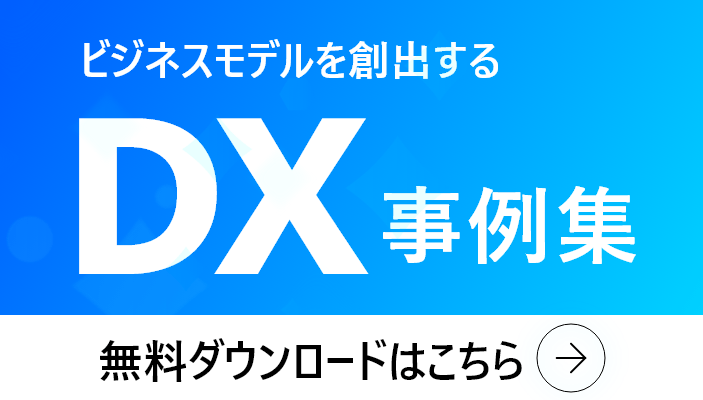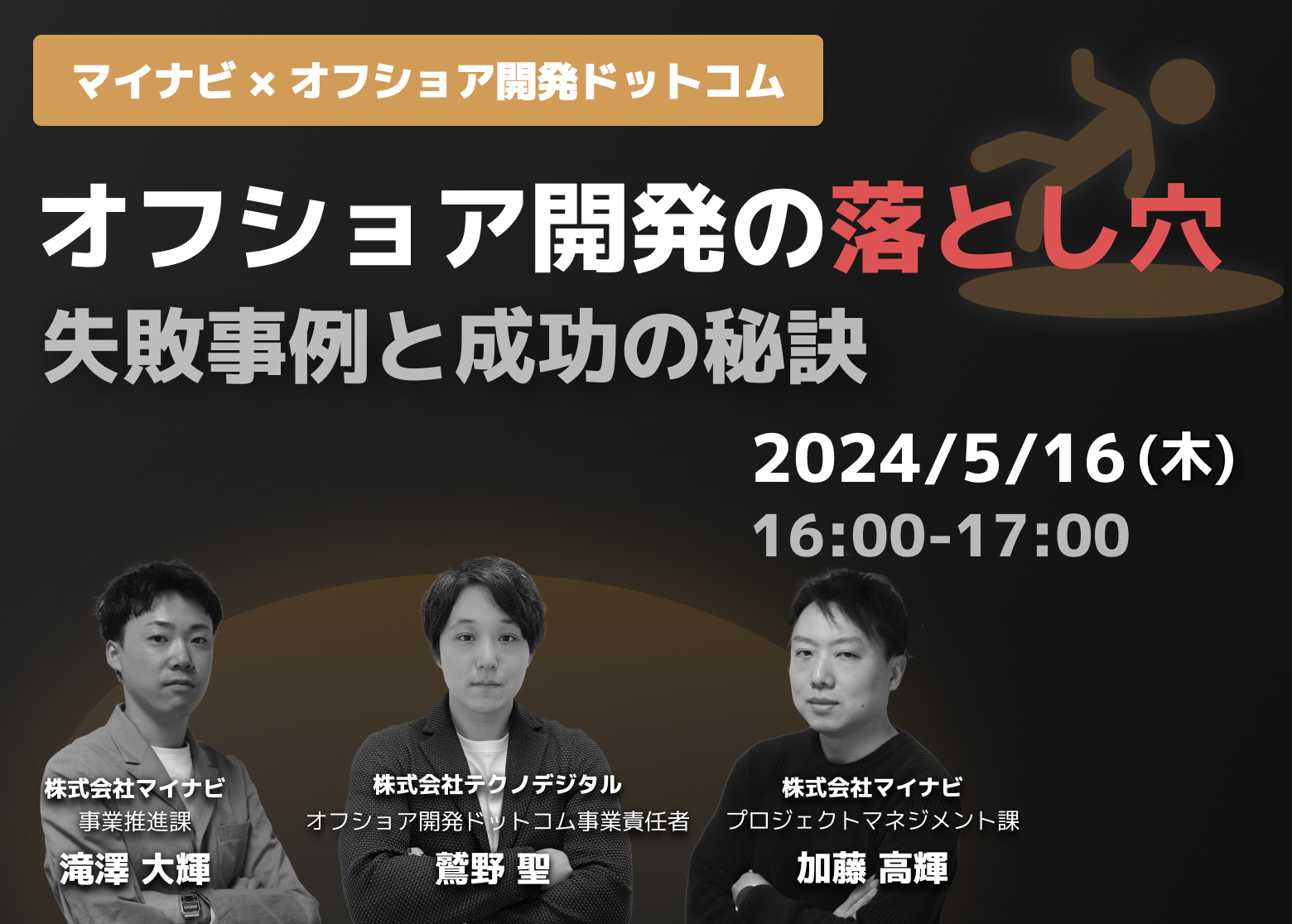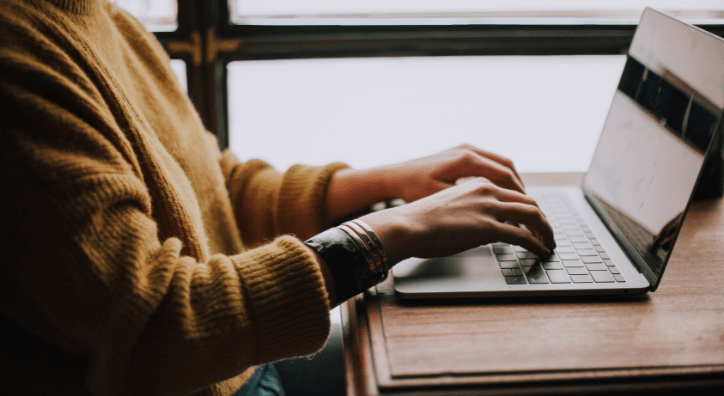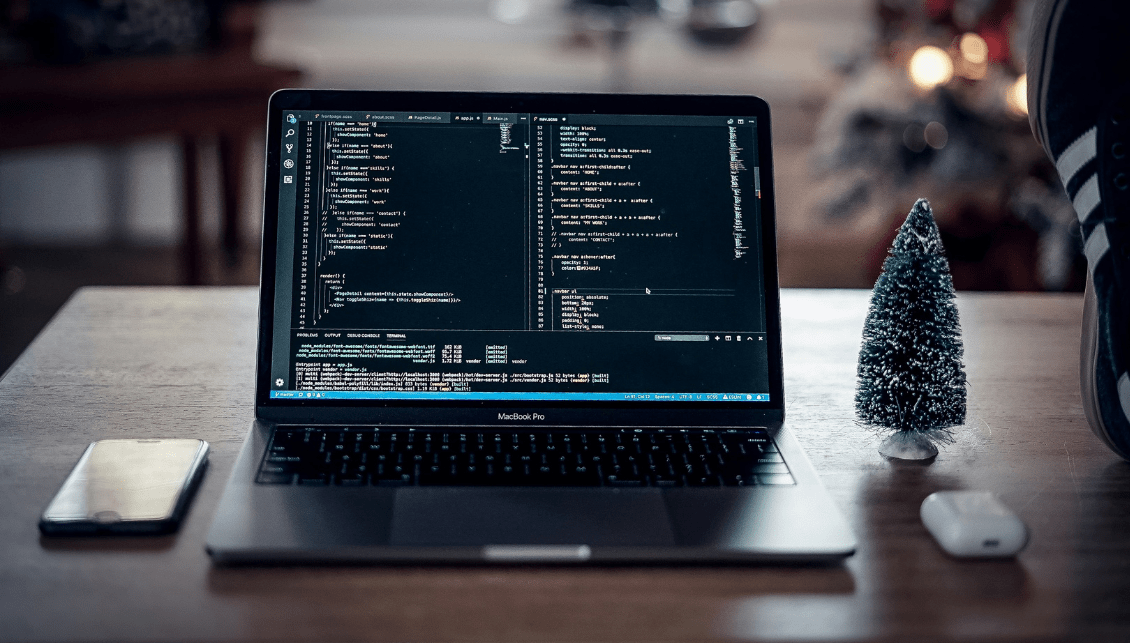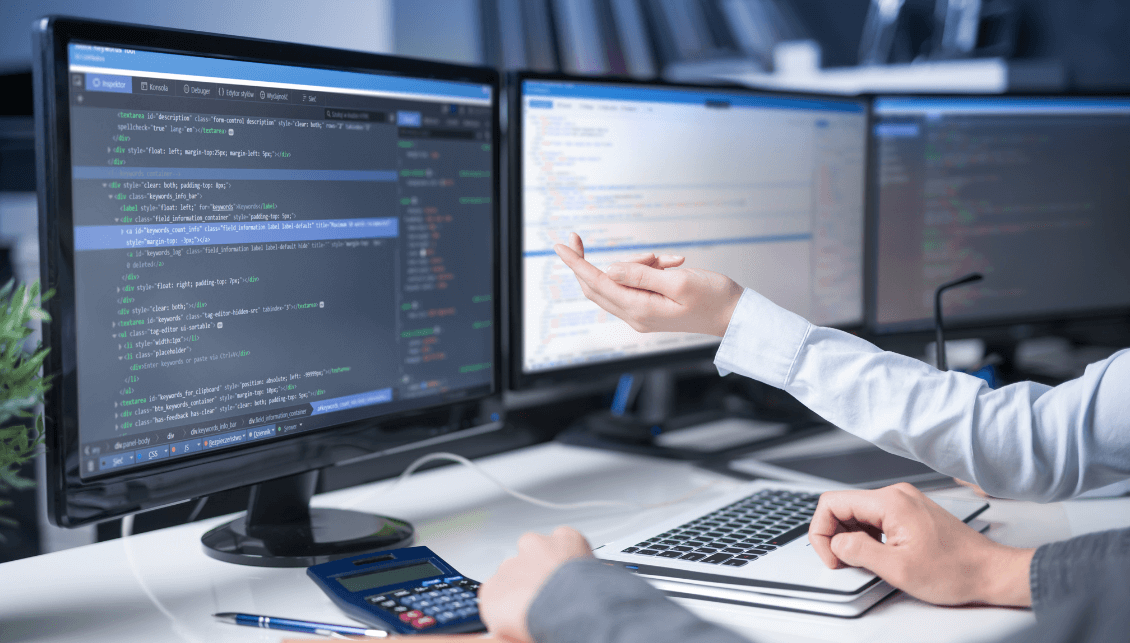システム開発の外注を検討している方にとって、スケジュールの把握は重要なポイントです。本記事では、システム開発の期間の目安や工程、システム開発を依頼する際にスケジュール面で押さえておくべきポイントを紹介します。
この記事を通じて、システム開発のスケジュールをしっかりと把握し、プロジェクトの成功に役立てましょう。
システム開発にかかる期間の目安
まずはシステム開発の工程ごとに、かかる期間やスケジュールの目安を見ていきましょう。
システム開発の工程と期間の目安
以下の工程ごとに、その概要とスケジュールの目安を紹介します。
- 要件定義
- 開発
- 運用・保守
要件定義
要件定義とは、開発するシステムの前提条件や機能などを明確にする作業です。
一般的には1~2ヶ月程度かかることが多いですが、システムの要件によって変動します。規模が大きかったり、複雑だったりするシステムほど、要件定義にかかるスケジュールは長いです。
開発
開発工程では、要件定義で明確にした概要を基にシステムを設計し、納品します。
開発工程には以下のような工程が含まれます。
- 基本設計:システムの全体構造や画面操作時の仕様を設計する工程
- 詳細設計:エンジニア向けに具体的な実装方法などを検討する工程
- プログラミング:設計書に基づいて実際にコードを書き、システムを構築する工程
- テスト:開発したシステムが要件を満たしているか、不具合がないかを確認する工程
- リリース:完成したシステムを導入する工程
全体を通して、3~6ヶ月程度かかることが多いです。要件定義と同じく、開発するシステムの規模が大きいほどスケジュールは長いです。
運用・保守
運用・保守は、システムがリリースされた後の継続的なサポートと改善を行う工程です。
システムを利用する限り継続的に発生し続ける工程であるため、期間はシステムの稼働期間に応じて違います。
アジャイル開発の場合
アジャイル開発とは、開発する機能ごとに開発サイクルを分割して(スプリント)、短期間のスプリントを繰り返す開発手法で、これにより柔軟に開発を進めることができます。
各スプリントは通常2~4週間で、以下のような工程が含まれます。
- 計画:スプリントの目標を設定し、タスクを洗い出す
- 開発:計画に基づいて機能を実装する
- テスト:実装した機能をテストし、不具合を修正する
- レビュー:スプリントの成果を評価し、次のスプリントに向けた改善点を洗い出す
スケジュールが変動するポイント
システム開発のスケジュールは、以下の要因によって変動することがあります。
開発する機能の数や複雑さ
開発する機能が多いほど、またその複雑さが増すほど、開発期間は長くなります。機能の優先順位を明確にし、段階的に実装することでスケジュールを管理します。
関係者・ステークホルダーの数
プロジェクトに関与する関係者やステークホルダーが多い場合、意思決定や調整に時間がかかることがあります。定期的なコミュニケーションと明確な役割分担が重要です。
連携するシステムやその内容
既存のシステムとの連携が必要な場合、その内容や複雑さによって開発期間が影響を受けます。連携部分の設計とテストに十分な時間を確保することが求められます。
物理的な開発条件
開発するシステムやインフラ環境に物理的な条件や制約がある場合、スケジュールに影響を与えることがあります。開発着手前に確認し、効率的に作業環境を整えることが重要です。
スケジュールの管理・作成方法
システム開発会社では、システム開発のスケジュールを管理したり、依頼者へ開発スケジュールを共有したりする際、ツールや管理手法を利用することも多いです。
このため、システム開発の依頼者がプロジェクトの全体スケジュールや各タスクの進捗を把握するにあたり、一般的なスケジュールの管理手法を知っておくと良いでしょう。
ここでは、システム開発のスケジュール管理によく使われる手法「WBS」と「ガントチャート」について説明します。
WBSとは
WBS(Work Breakdown Structure)は、プロジェクトの作業内容をタスク単位で分解する手法です。
各タスクの開始日、終了日、担当者を明確にすることで、全体の進捗を管理しやすくします。
ガントチャートとは
ガントチャートは、WBSで整理した各タスクおよびプロジェクト全体のスケジュールを可視化する手法です。縦軸にタスク、横軸に時間を配置し、各タスクの進捗状況をバーで示します。
ガントチャートによって、プロジェクトの進捗状況を一目で把握しやすくなります。
スケジュール管理のポイント・注意点
最後に、システム開発におけるスケジュール管理のポイントを紹介します。開発プロジェクトをスケジュール通り進めるためにも、システム開発会社が以下のような点を考慮しているか、確認すると良いでしょう。
打ち合わせや確認のスケジュールを含める
開発プロジェクトの進行には、定期的な打ち合わせやレビューが欠かせません。これらの定期作業をスケジュールに組み込むことで、進捗状況の確認や問題点の早期発見が可能になります。
担当者と密に連絡を取る
システム開発会社の担当者と密に連絡を取り合うことで進捗状況を把握し、問題が発生した際に迅速に確認できます。定期的なミーティングやチャットツールなどを活用して、コミュニケーションを円滑に保ちましょう。
完了条件を明確にする
各タスクの完了条件を明確に定義することで、システム開発会社と依頼者の間の認識が合いやすくなります。
スケジュール変動に応じたリカバリー策を用意する
プロジェクトの進行中には、予期せぬ事態や変更が発生することがあります。こうした変動に対応するために、リカバリー策を事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
- システム開発の工程と期間の目安は要件定義に1~2ヶ月、開発に3~6ヶ月、運用・保守に継続的な時間が必要
- アジャイル開発では短期間のスプリント(2~4週間)を繰り返し、計画、開発、テスト、レビューを行う
- スケジュール変動の要因には機能の数や複雑さ、関係者の数、連携システムの内容、物理的な開発条件がある
- スケジュール管理手法は作業内容をタスク単位で分解するWBS、スケジュールの可視化を行うガントチャートがある
- スケジュール管理のポイントは定期的な打ち合わせ、担当者との密な連絡、完了条件の明確化、リカバリー策の準備の4つ
Recommended Materials
おすすめ資料