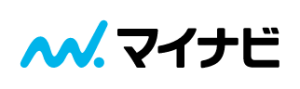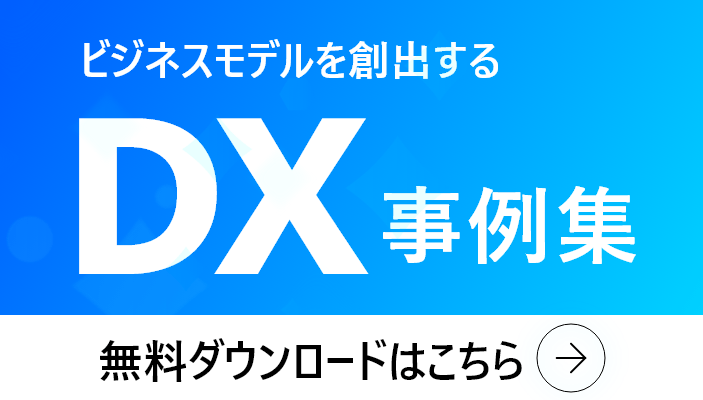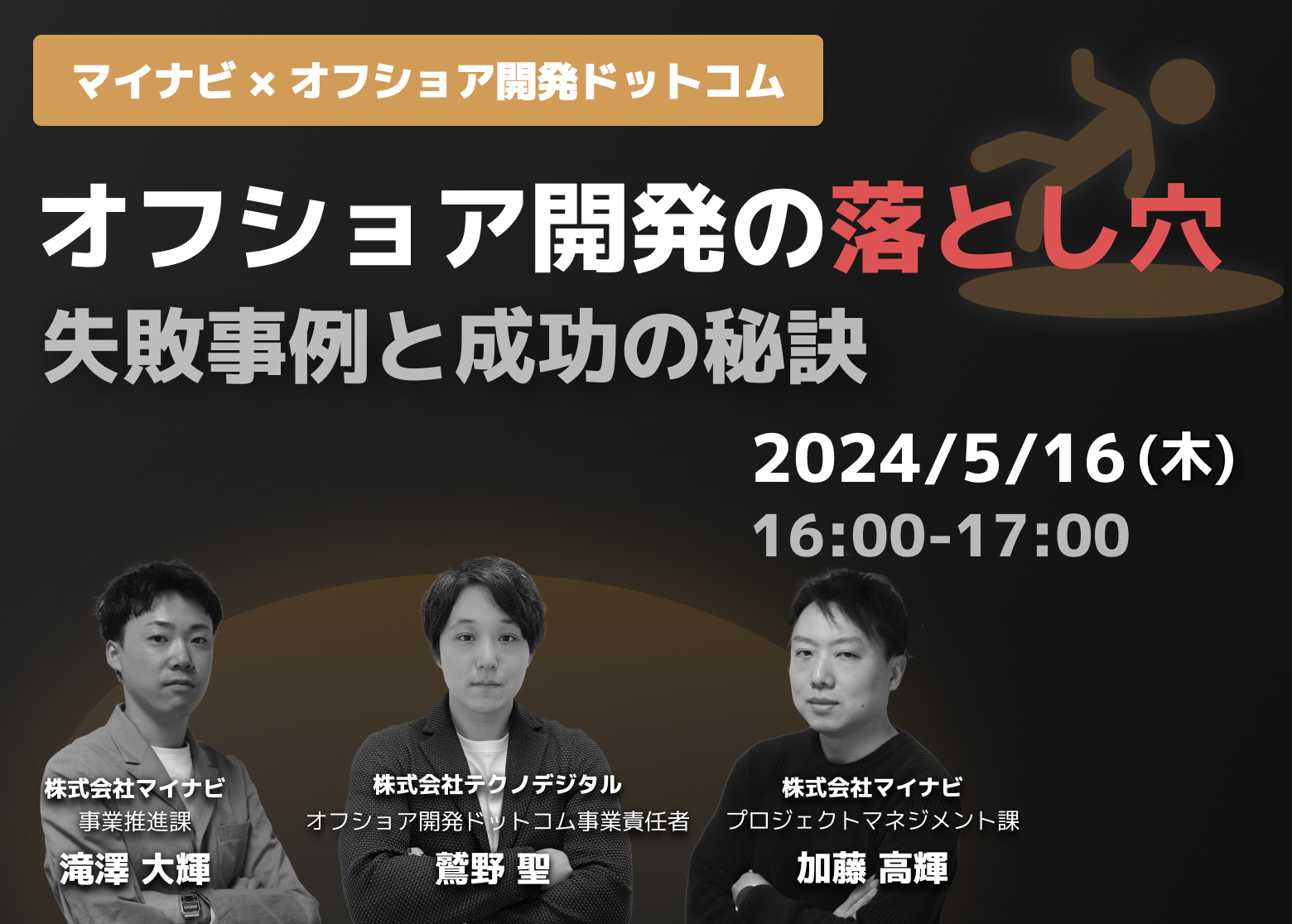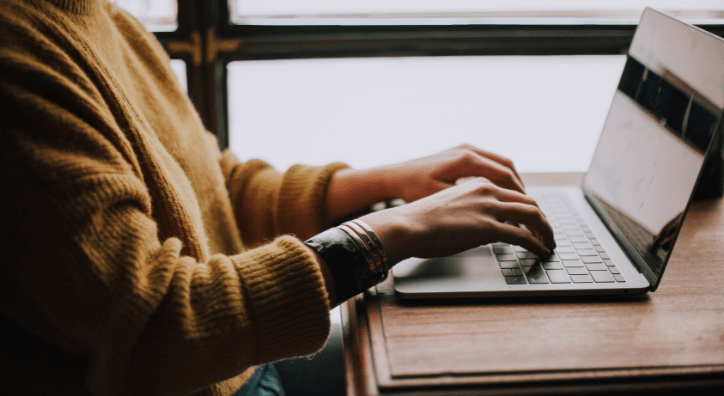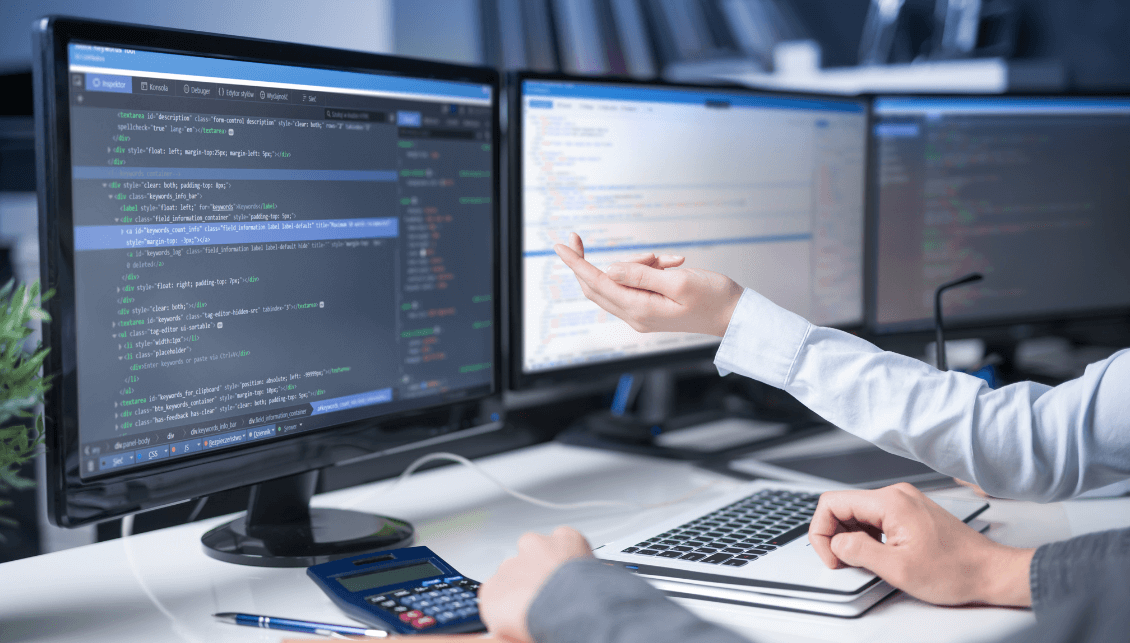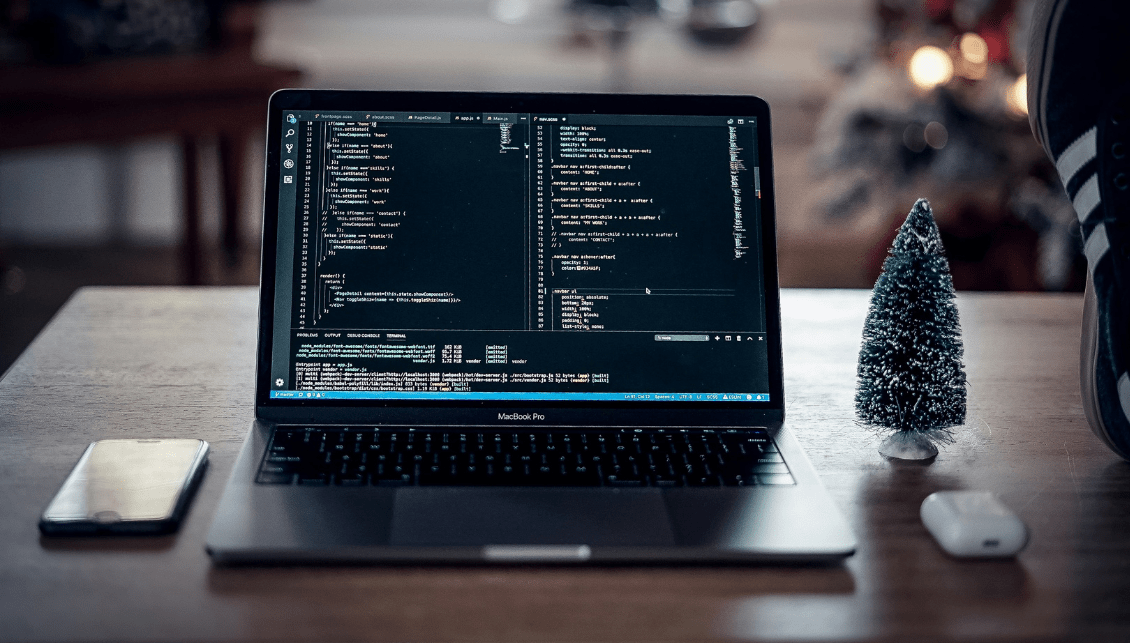- システム開発の要件定義の意味が知りたい
- 要件定義はどのように決めるのか理解したい
- 要件定義をするために自社で必要なことは?
システム開発における要件定義とは、システムを開発する目的や求める機能を具体的に定義する作業のことを言います。要件定義は、システム開発を進める基盤となるもので、プロジェクトの成功に欠かせないステップです。
要件定義に抜け漏れ・曖昧さ残っていると、トラブルが発生する原因になってしまいます。要件定義を適切に行うには、依頼者側の協力が必要不可欠です。
この記事では、システム開発における要件定義とは何か、具体的な進め方やスムーズに行うポイントを解説します。
要件定義について正しく理解したい方や具体的な進め方を知りたい方は、ぜひ当記事をご参照ください。最後まで読めば、納得できる要件定義を決めるために、自社で必要なことがわかるでしょう。
INDEX 目次
システム開発の要件定義とは
システム開発の要件定義とは、開発するシステムに必要な機能や仕様を明確化・具体化する作業を指します。
要件定義はシステム開発の基盤となるもので、プロジェクトの成功を左右する最も重要なステップです。そのため、ほとんどのシステム開発会社がプロジェクトの最初の工程として、要件定義を行ないます。
システム開発における要件定義の作業内容は、依頼者が抱えている課題や導入したい機能などをヒアリングし、プログラミングに必要な「設計書」に落とし込むことが一般的です。
設計書には、導入する機能や性能、制約条件など、システム開発に必要な要素が記載されており、設計書をもとに具体的な開発計画が作成されます。システム開発会社によっては、作成した要件定義を踏まえて、より詳しい見積もりを算出する場合もあります。
要件定義に必要な機能の抜け漏れや曖昧さが残っていると、開発期間の延期や想定とは違うシステムが納品されるなど、トラブルが発生する可能性が高くなります。
システム開発のトラブルの原因は、要件定義から発生することがほとんどと言われています。そのため、要件定義ではシステム開発会社との綿密なコミュニケーションが必要不可欠で、依頼者側は要件定義に関してある程度の理解が必要となります。
要求定義との違い
システム開発の要件定義を行うには、始めに「要求定義」という作業が行われます。どちらも似たような言葉ですが、それぞれの意味が異なるので、事前に把握しておきましょう。
先ほど解説したように、要件定義はシステムの具体的な機能や条件を定義する作業です。一方、要求定義はシステム開発の背景にある課題や要望を収集し、システム化によって実現化したいことを整理する作業を指します。
一般的には、要求定義→要件定義の順番で行われます。システム開発で実現したいことを整理(=要求定義)したうえで、それを実現するために必要な機能を決定(=要件定義)する流れです。
例えば、「紙で処理している請求書の押印作業をシステム化し、コストを削減して業務を効率化させたい」という依頼を受けた場合、要求定義と要件定義の違いを見ていきましょう。
| 要求定義 | 要件定義 |
|---|---|
|
コスト削減 業務効率化 |
システム上で請求書を発行する機能 発行した請求書を、システム上で押印する機能 押印が完了した請求書を、経理部へ通知する機能 etc. |
要求定義は、システム開発の依頼者が行なうとスムーズになります。依頼者が要求事項をまとめておくと、システム開発会社が要求事項に基づいて、どのような機能が必要か技術的に実現可能か検討し、要件定義をまとめてくれます。
注意点として、要求定義にまとめた要求内容が全て実現できるとは限りません。予算・開発期間・技術的な実現可能性などを考慮したうえで、「これなら実際に開発できる」とシステム開発会社が判断したものが、要件定義にまとめられます。
そのため、要求定義を作成する際は必要な機能に優先順位を決めておくと、双方納得できる要件定義が作成でき、よりスムーズにシステム開発を進めることができるでしょう。
要件定義の流れ
要件定義の概要を理解したところで、ここからは要件定義を進める方法を解説していきます。
要件定義は、以下のような流れで行われます。
要件定義の流れ
- ヒアリング
- 要求の分析・調整
- 要件定義書の作成
- 設計書の作成
要件定義の流れを把握しておくと、要件定義の内容が理解しやすくなり、要求通りに開発されるかどうか判断できます。
ヒアリング
前章で解説したように、要件定義を行うためには要求定義を行う必要があります。そのために、まずは依頼者側の要求をヒアリングしていきます。
具体的には、システム開発会社が依頼者に対して、ビジネス概要や業務内容、現状の課題、要望などを確認します。
依頼者側は、事前に以下の点を整理しておくと、システム開発会社はスムーズに要件定義を進められます。
- Why:システム開発の背景・理由
- What:課題、改善したい点、システム開発によって実現したいこと
- Where:開発を希望する範囲はどこまでか
- Who:開発システムの利用者・運用者が誰か
- When:システムの開発はいつまでに必要か
- How much:システム開発の予算はどのくらいか
上記は、どのようなシステムを開発したいか確認するための要素です。もし既存システムを利用している場合は、外部サービスとの連携やセキュリティー規定など、システム環境に関するヒアリングも行われるので、合わせて整理しておくといいでしょう。
要求の分析・調整
ヒアリングが完了したら、その内容を整理して要求定義をまとめていきます。システム開発会社は依頼者の要求内容に対して、技術的な実現可能性や予算などを考慮し、実現可能な要求内容や実装方法を整理します。
要求内容によっては、技術的な難易度が高く開発が難しかったり、全ての要求を実装すると予算オーバーになったりするかもしれません。このような場合は、実装したい機能を減らしたり代替案となる機能に変えたりして、双方が合意できる要求定義に調整します。
そのため、要求内容が全て通らない場合を見越して、要求内容の優先順位を付けておくと、予算内で理想に近い要求定義が作成しやすくなります。
要件定義書の作成
要求定義が決まったら、実際に要件定義書を作成していきます。
一般的な要件定義書には、以下のような項目が記載されています。
- システム開発の目的 システム開発の依頼背景、解決したい課題や達成したい目標
- システムの導入環境 ネットワーク環境やデータベースの種類など、システムの導入に必要な条件
- 機能要件 実装したい機能の具体的な内容・定義
- 非機能要件 ユーザビリティ・拡張性、運用・保守、移行性・セキュリティなど、機能要件に含まれない要件の定義
- 開発工数 システム開発にかかる作業量・開発時間の見積もり
- 開発スケジュール システム開発の各工程に必要な期間と期限
- プロジェクトメンバー システム開発に関わるエンジニアの情報・役割
- 予算 人件費・ハードウェア代・サーバー代など、システム開発に必要な費用の総額
- システム開発者と依頼者の連絡方法・頻度 依頼者とシステム開発会社との連絡手段や進捗報告の方法・スケジュール
- 設計書 業務フロー図・画面構成図・デザインデータなど、実際にシステムを作成するための詳細内容・図面
システム開発の目的、課題・開発目標、システム概要、予算は、要求定義の作成時点で決定した内容です。それ以外は、システム開発会社が要求定義を踏まえて作成していきます。
システム開発は、この要件定義書を基に進めていきます。要件定義書に抜け漏れや曖昧さいがあると、開発期限の延期や想定とは異なるシステムが納品されるなど、トラブルの発生に繋がります。
そのため、要件定義書が完成したら各項目を確認し、ちょっとした不明点や疑問点を見つけたら、1つずつシステム開発会社に確認しましょう。
要件定義をスムーズに進めるためのポイント
ここまで、システム開発における要件定義の概要と作成の流れを解説しました。
求めるシステムを開発してもらうためには、抜け漏れや曖昧さがない要件定義書を作成することが重要です。そのためには、依頼者側は以下のポイントを押さえる必要があります。
要件定義を進めるポイント
- システム開発会社とのコミュニケーションを丁寧に行う
- IT知識を身に付ける
- 業務イメージを分かりやすく伝える
システム開発会社がスムーズに要件定義を進められるよう、上記のポイントを1つずつ確認しておきましょう。
システム開発会社とコミュニケーションをとる
要件定義では、システム開発会社がヒアリングを行ない、開発に必要な要件を引き出してくれますが、システム開発会社が気付きにくい要件もあります。
システム開発会社に要件定義を丸投げするのではなく、依頼者側は要件を事前に整理したり質問に丁寧に回答したりして、協力的な姿勢を持つことが重要です。
また、一度完成した要検定義書はしっかりと目を通し、少しでも気になる点が見つかったら、システム開発会社に1つずつ聞きましょう。
システム開発会社と密にコミュニケーションを取ることで、要件定義の抜け漏れ・曖昧さを回避しやすくなります。
IT知識を身に付ける
先ほど解説したように、システム開発を成功させるには、システム開発会社と依頼者の綿密なコミュニケーションが重要です。そのためには、システム開発会社はもちろん、依頼者側もある程度のIT知識が求められます。
要件定義に限らず、システム開発では依頼者に判断を委ねられることが多々あります。もしIT知識が不足していると、要件定義の抜け漏れ・曖昧さを見つけることが難しくなります。
そのため、依頼者側の担当者は、事前にIT知識を身に付けておきましょう。もしくは、IT知識を持ち合わせている従業員を、システム開発の担当者に任命することもおすすめです。
業務イメージを分かりやすく伝える
抜け漏れ・曖昧さのない要件定義を作成するには、システム開発会社が依頼者側のビジネスや業務内容を深く理解していることも重要です。そのためには、依頼者側の情報を共有する必要があります。
例えば、小売業のシステムの開発であれば販売手法や受発注業務、製造業のシステムの開発なら製造に必要な設備や技術・行程や使用する資材などが挙げられます。
システム開発会社が依頼者側と同じような依頼を受けた経験があれば、業界情報や業務内容をある程度理解している可能性はあります。その上で、依頼者側の情報を可能な限り共有すれば、より具体的な要件定義を作成することが可能です。
システム開発会社は、依頼者の業界や業務内容に精通しているとは限りません。システム開発会社からヒアリングを受ける際は、自社の前提知識や業務内容をわかりやすく伝えることを心掛けましょう。
まとめ
この記事では、システム開発における要件定義の概要や作成方法を解説しました。
下記に、要件定義を理解するためのポイントをまとめておきます。
要件定義のポイントまとめ
- 要件定義はシステム開発を進める基盤となる作業である
- システム開発が失敗してしまう原因は、ほとんど要件定義から発生している
- システム開発を成功させる鍵は、要件定義の抜け漏れ・曖昧さをなくすこと
- 要件定義の作成には、依頼者側の協力が必要不可欠である
システム開発会社と依頼者、双方が納得できる要件定義を決められると、プロジェクトの成功に大きく近づくでしょう。
そのためにも、自社のビジネスや業務内容を可能な限り共有し、システム開発会社の質問には丁寧に回答するなど、綿密なコミュニケーションを心がけてください。
「要件定義を丁寧に決めてくれるシステム開発会社が知りたい」「システム開発は初めてで、どこに依頼したらいいかわからない」という方は、株式会社マイナビにご相談ください。予算や目的をヒアリングのうえ、最適なご提案内容を提示いたします。
要件定義で必要なことや進め方が知りたいなど、ちょっとした質問だけでもかまいません。ぜひ一度当社にご相談ください。
Recommended Materials
おすすめ資料