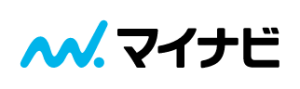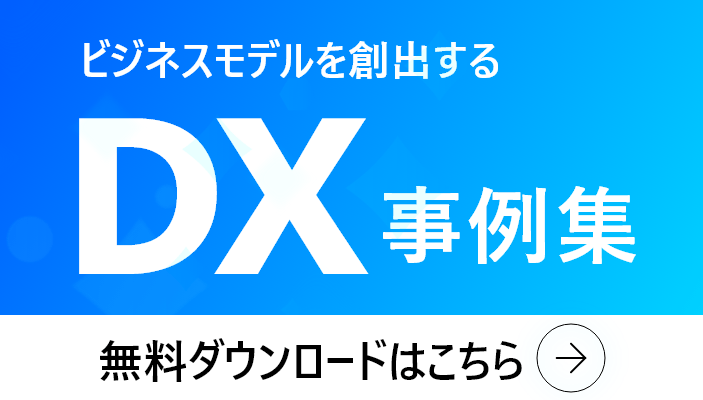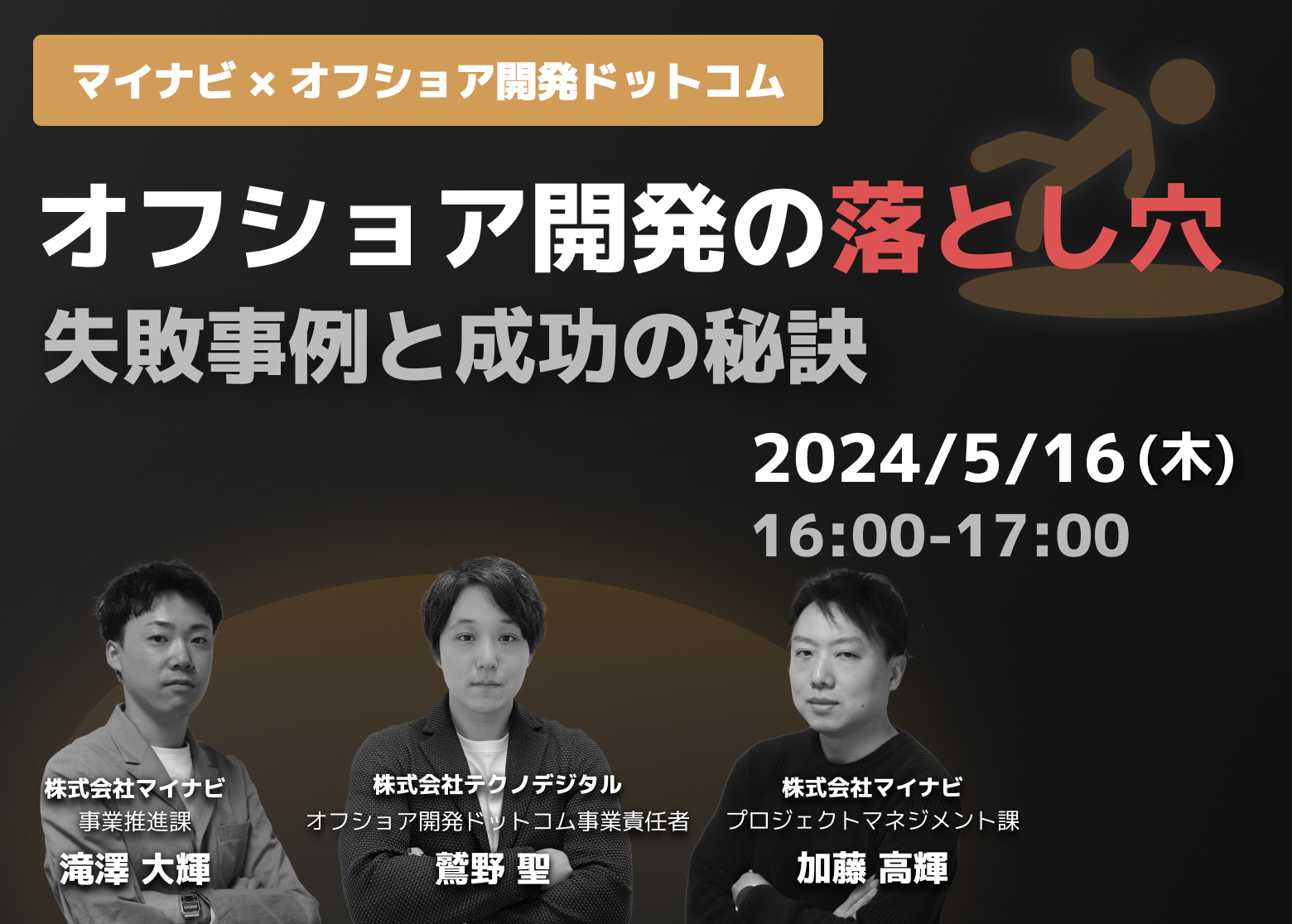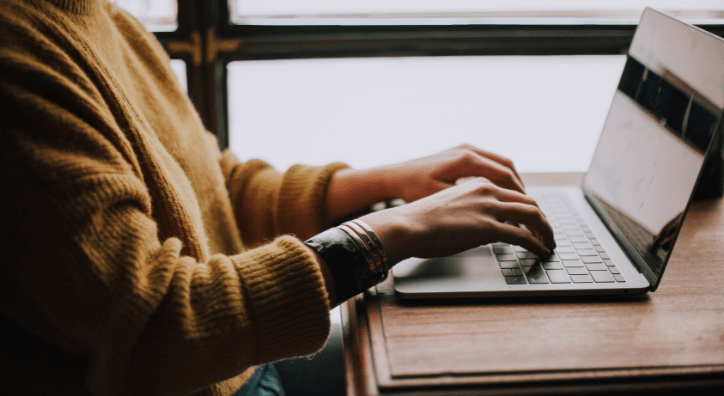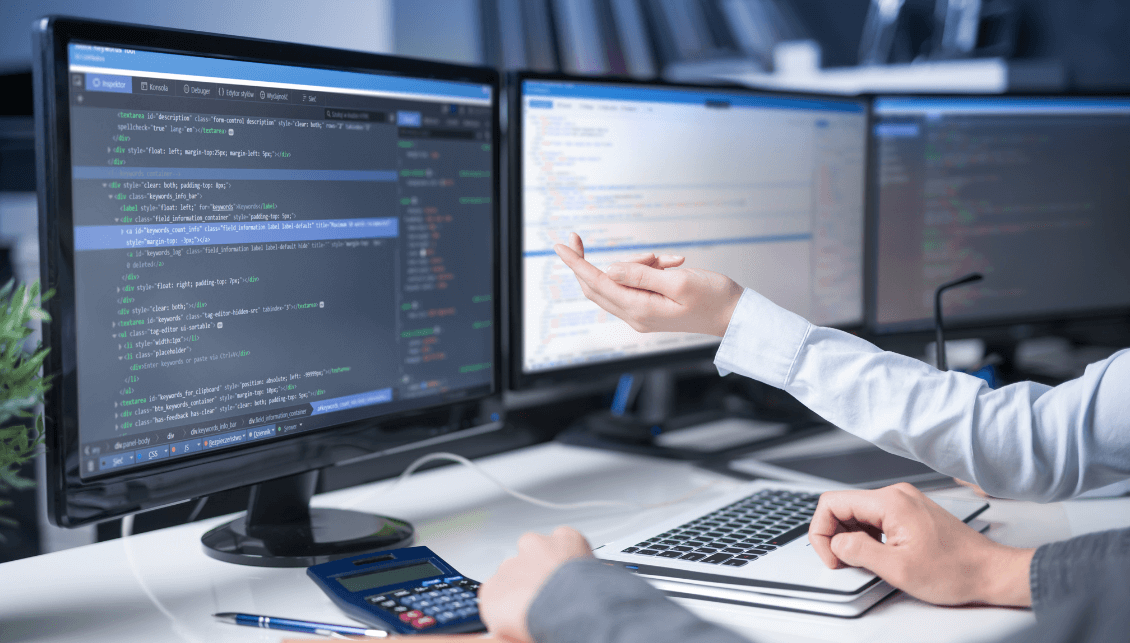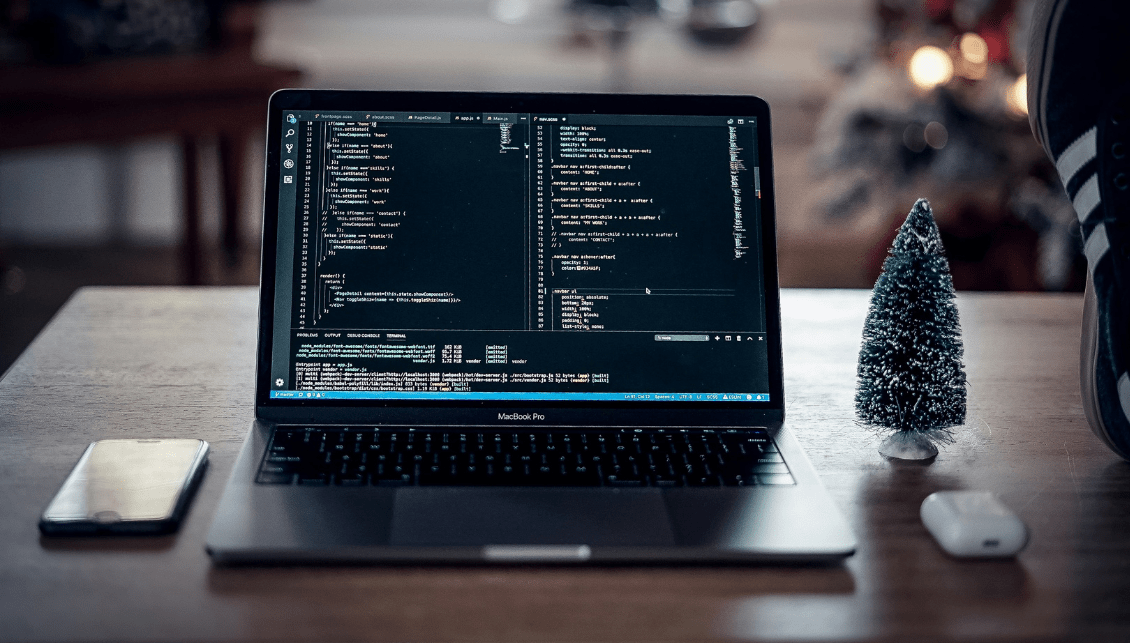システム開発にはさまざまな開発手法があり、開発するシステムの特徴によって適切な手法を選ぶことが大切です。
本記事では、主なシステム開発手法やそれぞれのメリット・デメリット、手法の選び方のポイントなどを紹介します。システム開発の手法についての理解を深める一助になれば幸いです。
INDEX 目次
【システム開発の手法比較一覧】ウォーターフォール、アジャイル、プロトタイプ、スパイラル、DevOps、MVCモデル
まずは、主なシステム開発の手法と、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
| 手法 | 概要 |
|---|---|
| ウォーターフォール | 工程を順番通りに進める開発手法 |
| アジャイル | 短期間の開発サイクルを繰り返す開発手法 |
| スパイラル | 段階的に試作品を作成する開発手法 |
| プロトタイピング | 簡易的な試作品で検証・改良を繰り返す開発手法 |
| DevOps | 開発と運用を統合する開発手法 |
| MVCモデル | システムを役割(モデル、ビュー、コントローラー)に分けて設計する開発手法 |
ウォータフォール
ウォーターフォールは、各開発工程が完了してから順番通りに開発を進行する開発手法です。
| メリット | ・計画や進捗が分かりやすい ・ドキュメント作成を重視するため、確認や引き継ぎがしやすい |
| デメリット | ・開発の初期段階で要件を確定する必要があり、あとで変更しにくい |
| おすすめのシステム | ・要件が明確で変更が少ないシステム ・大規模な開発や政府関連のプロジェクトなど、厳密な計画と管理が求められるシステム |
アジャイル
アジャイルは、機能や作業内容ごとに開発サイクルを分けて、短期間の開発サイクルを繰り返しながら進行する開発手法です。
| メリット | ・要件の変更に柔軟に対応可能 ・フィードバックを通じてシステムを改善しやすい ・短いサイクルで開発を進めるため、問題の早期発見や対策の検討がしやすい |
| デメリット | ・全体の計画が曖昧になりがちで、進捗を把握しにくい場合もある ・スピードを優先するため、ドキュメント作成の優先度が低い ・定期的に密なコミュニケーションが必要 |
| おすすめのシステム | ・要件が頻繁に変わるシステム ・フィードバックを受けながら改善していきたいシステム ・スタートアップ企業や新規サービスの開発など、スピードが求められるシステム |
スパイラル
スパイラルは、ウォーターフォールとアジャイルを組み合わせたような開発手法です。この手法では、いくつかの段階に分けて、段階ごとに試作品(プロトタイプ)を作成し、完了後にリリースをします。
| メリット | ・要件の変更や新しい技術の導入に柔軟に対応しやすい ・段階的に進捗を確認しやすい ・フィードバックを反映しやすい |
| デメリット | ・プロトタイプの作成に時間や費用がかかる ・段階ごとに開発を進めるため、全体の完成形が見えにくくなることがある |
| おすすめのシステム | ・要件が不明確なシステム ・新技術の導入を伴うシステム |
プロトタイピング
プロトタイピングは、簡易的な試作品(プロトタイプ)を作成し、検証を繰り返しながらシステムを完成させる開発手法です。
| メリット | ・プロトタイプを通じて、問題や改善すべき点を早期に発見できる ・フィードバックを反映しながら改善することにより、ニーズに合うシステムが完成しやすい ・要件の変更や新しいアイデアを取り入れやすく、柔軟な開発が可能 |
| デメリット | ・プロトタイプの作成に時間や費用がかかる ・プロトタイプの改良を繰り返すことで、全体の完成形が見えにくくなることがある |
| おすすめのシステム | ・要件が不明確なシステム ・フィードバックと改良を重視するシステム ・新しい技術やコンセプトを試す場合や、操作性が重要なシステム |
DevOps
DevOpsは、システム開発と運用を統合する開発手法です。開発と運用の管理を一貫することで、品質向上や工数の短縮を目指します。
| メリット | ・運用効率の向上により、迅速なリリースにつながりやすい ・不具合の早期発見や、スムーズなトラブル対応につながりやすい |
| デメリット | ・自動化ツールやインフラの整備に初期コストがかかり、導入時の投資が必要な場合がある |
| おすすめのシステム | ・頻繁なリリースが必要なシステム ・迅速な市場投入が必要なプロジェクト |
MVCモデル
MVCモデル(Model-View-)は、システムを「モデル(Model)」「ビュー(View)」「コントローラー(Controller)」の3つに分けて設計する開発手法です。
「モデル」はデータの取得・登録・更新削除といったデータのやり取り、「ビュー」はシステムの利用者が見る画面(インターフェース)、「コントローラー」は「モデル」と「ビュー」を指示する部分を示します。
| メリット | ・分業や流用がしやすく、開発効率の向上につながる ・各要素が独立しているため、特定の部分に変更を加えても他の部分に影響を与えにくく、保守が容易 |
| デメリット | ・初期設計が複雑になりがちで、時間がかかる ・各要素間の通信が増えるため、システム全体のパフォーマンスが低下する可能性がある |
| おすすめのシステム | ・操作画面が複雑なシステム ・大規模な法人システム ・複数の開発チームが関与するシステム |
システム開発の手法の選び方
ここまで紹介したシステム開発の手法のなかで「自分が開発するシステムではどの手法を選ぶと良いか」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。ここでは、開発手法の選び方のポイントを説明します。
システムの規模や複雑さ
まずは、開発するシステムの規模や複雑さに応じて、開発手法を選びましょう。
一般的には、大規模で複雑なプロジェクトは「ウォーターフォール型」や「スパイラル型」、小規模で迅速な開発が求められるプロジェクトには「アジャイル型」や「プロトタイプ型」が向いている傾向があります。
要件の明確さや変更の頻度
要件が明確で変更が少ないプロジェクトは、要件を確定してから開発を進める「ウォーターフォール型」がおすすめです。
逆に、要件が不明確で頻繁に変更が発生するプロジェクトには、変更などに柔軟に対応できるアジャイル型やプロトタイプ型がおすすめです。
リスク管理の重要性
厳格なリスク管理が重要なプロジェクトは、こまめにリスクを評価しながら進行する「スパイラル型」を検討すると良いでしょう。
逆に、要件が不明確で頻繁に変更が発生するプロジェクトには、変更などに柔軟に対応できるアジャイル型やプロトタイプ型がおすすめです。
フィードバックの頻度
開発プロジェクトにかけられる負荷によっても、適する開発手法が違います。
特に「アジャイル型」や「プロトタイプ型」では、こまめな確認やフィードバックが必要です。システム開発の依頼者と開発者の間で、密なコミュニケーションが断続的に求められるので、負荷をかけても納得のいくシステムを開発したい場合に検討することをおすすめします。
開発スピードの速さ
開発するシステムの領域や分野などによって、スピード重視でリリースするべきか、それとも慎重にリリースをするべきかといった、求める開発のスピード感に違いがあるでしょう。
スピードが求められるプロジェクトは、こまめにリリースをしながら改善を継続できる「アジャイル型」や「DevOps」がおすすめです。
システム開発会社選び・比較のポイント
開発手法の見当をつけたあとは、実際にシステム開発会社への相談や依頼を進めます。ここでは、システム開発会社の選び方のポイントを説明します。
類似実績や知見があるか
自社の業界やニーズに合った実績がある会社を選ぶと安心です。開発したいシステムに似た過去事例を持つシステム開発会社であれば、開発がスムーズに進む可能性も高くなります。
また開発手法によっては、システム開発会社の対応可否に違いがある場合があります。希望する開発手法での実績があるか、開発チームにスキルや知見があるかなども確認すると良いでしょう。
コミュニケーションが円滑か
システム開発の成功のためには、システム開発会社との円滑なコミュニケーションが欠かせません。
定期ミーティングの有無や報告のタイミング・方法などを確認しながら、対応が迅速なシステム開発会社を選ぶことがおすすめです。
費用が予算に合うか
複数のシステム開発会社から相見積もりをとり、費用を比較しましょう。
この際、機能や仕様などの前提条件に違いがあると比較が難しいため、同じ条件であることを確認しましょう。また、単純に費用の安いシステム開発を選ぶだけではなく、品質やサポート体制も考慮することが大切です。
サポート体制が十分か
システム開発はリリースして終わりではなく、不具合の修正や追加開発などを継続して行なうことが一般的です。
このため、長期的なサポート契約があるか、トラブル時の対応方針などを確認しながら、開発後の対応がしっかりしているシステム開発会社を選ぶと良いでしょう。
まとめ
- システム開発の手法には「ウォーターフォール」「アジャイル」「スパイラル」「プロトタイピング」「DevOps」「MVCモデル」がある
- システム開発の手法を選ぶ際は「システムの規模や複雑さ」「要件の明確さや変更の頻度」「スク管理の重要性」「フィードバックの頻度」「開発スピードの速さ」などを検討する
- システム開発会社を選ぶ際のポイントは「類似実績や知見」「コミュニケーションの円滑さ」「費用の予算適合」「サポート体制」
Recommended Materials
おすすめ資料