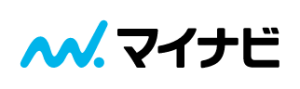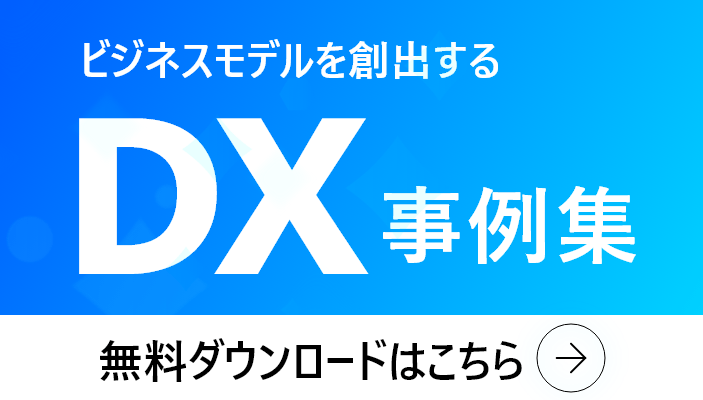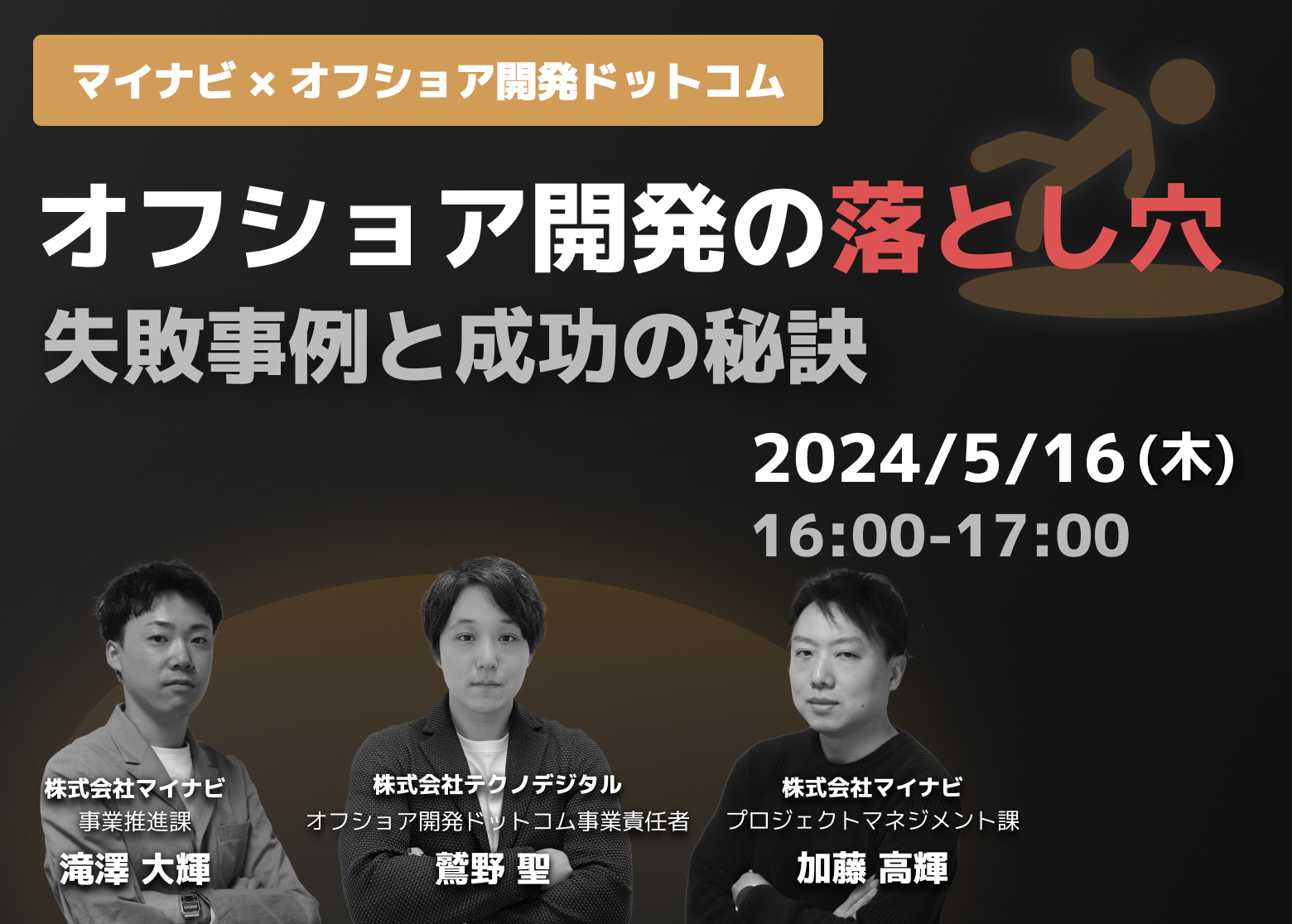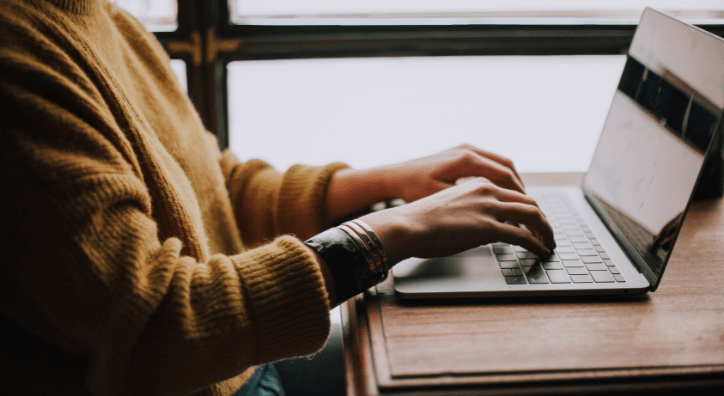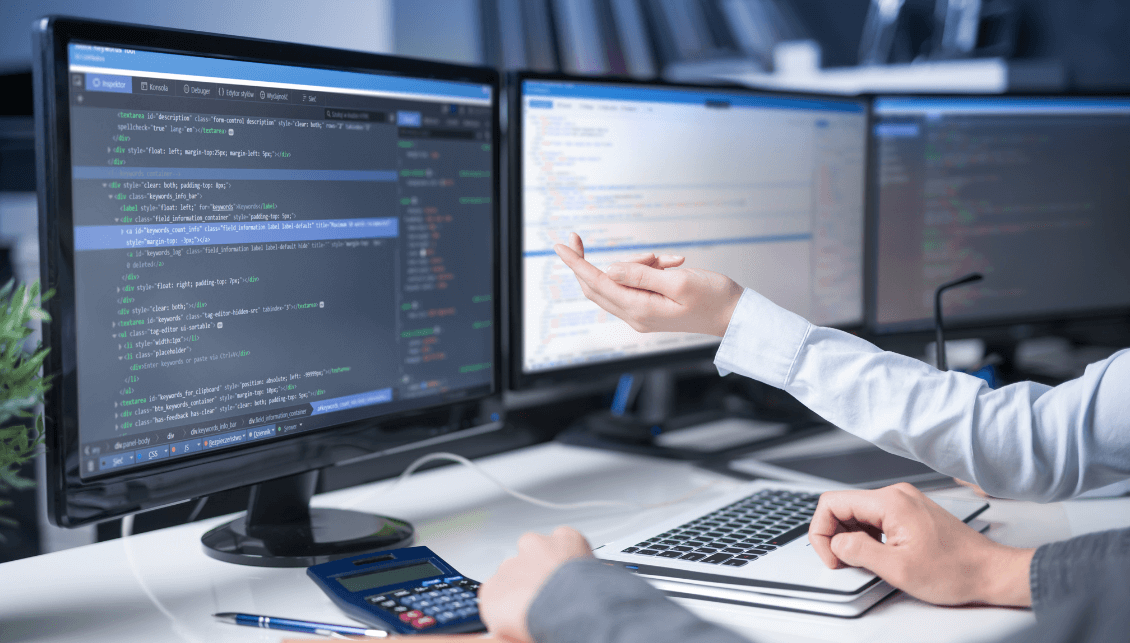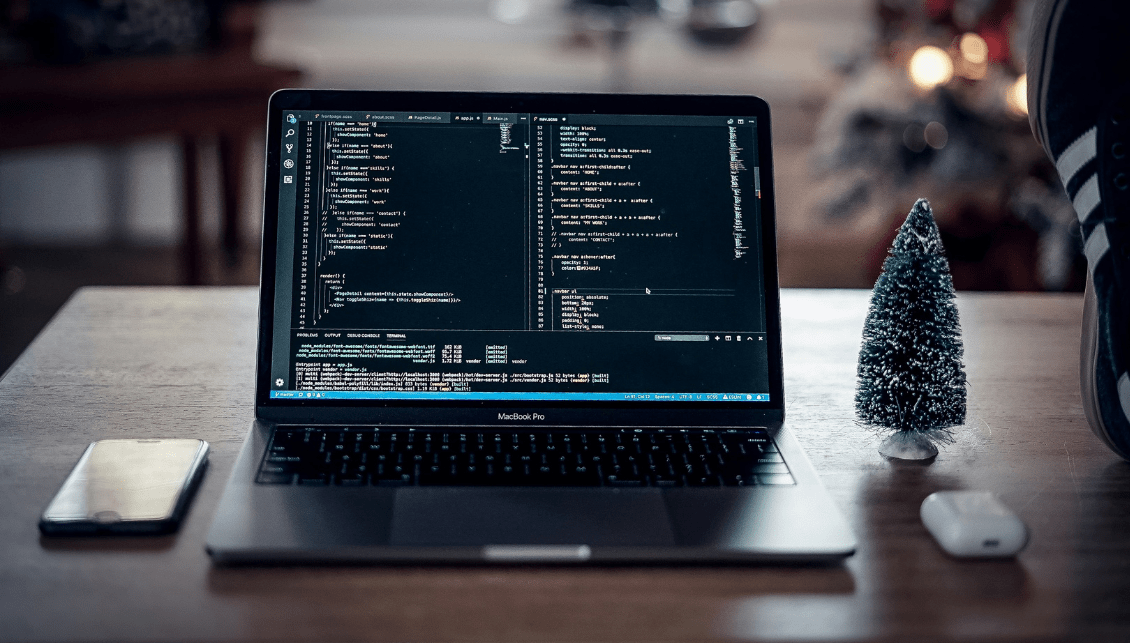システム開発における著作権は重要な問題であり、開発者や企業が保護すべき貴重な資産です。
システム開発の外注において、著作権がどのように扱われるか理解していないと、思わぬトラブルが起きてしまう可能性があります。
この記事では、システム開発における著作権を詳しく解説し、その重要性と保護のための手段を紹介します。
「システム開発を外注した場合、著作権はどう扱われるのか?」と疑問を抱いた方は、ぜひ当記事をご参照ください。

INDEX 目次
システム開発における著作権の帰属先
一般的に開発されたシステムやソフトウェアに関連した著作権は、その創作物を実際に生み出した個人または企業に帰属します。
以下に、システム開発のパターンに分けて、著作権の帰属先を解説していきます。
個人による開発の場合
個人が契約や雇用関係を通じてシステムの開発を行った場合、著作権はその個人本人に帰属します。
ただし、例外的な契約や法的取り決めがある場合はその範囲に従う必要があります。
会社による雇用関係の場合
会社に雇用されている開発者が会社の業務としてシステムを開発した場合、著作権はその会社に帰属することがほとんどです。
このような場合、契約や雇用規則に著作権の帰属に関する規定が明記されています。
契約に基づいた開発の場合
開発者や開発会社と顧客との間で契約が成立し、その契約に著作権に関する取り決めが含まれている場合、著作権の帰属先は契約に沿って定められることが一般的です。
契約書には明確な取り決めが記載され、その範囲内で著作権が取り扱われます。
著作権が帰属するメリットと帰属しないデメリット
続いては、著作権が自社に帰属するメリットと帰属しないデメリットを解説します。
それぞれ簡単にまとめると以下のとおりです。
| 帰属するメリット | 帰属しないデメリット |
|---|---|
|
|
それぞれ順番に見ていきましょう。
著作権が帰属するメリット
著作権が帰属するメリットは以下のとおりです。
- 法的保護が受けられる
- 商業的価値を確保できる
- 信頼性と信用を得られる
法的保護
著作権が帰属すると、その作品が著作権法によって保護されるため、他者による無断利用や模倣を防ぐことができます。
著作権を持つことで、法的手段を用いて権利を主張することが可能です。
商業的価値の確保
著作権は知的財産権の一形態であり、社会的・経済的価値を持ちます。
著作権を持つことで、作品の商業的な利用やライセンス供与による収益化が可能です。
信頼性と信用
著作権を持つことで、自身の作品に対する信頼性と信用が向上し、他者との交渉や取引において有利になることがあります。
著作権が帰属しないデメリット
著作権が帰属しないデメリットは、以下のとおりです。
- 無許可利用の危険性がある
- 商業的な機会を損失する
- 信頼性が低下する可能性がある
無許可利用の危険性
著作権が帰属しない場合、他者による無許可利用や模倣の危険性が高まります。
万が一、他者が自身の作品を無断で使用して損害が発生したとしても、法的な対応が難しくなります。
商業的な機会の損失
著作権が不明確な場合、作品の商業的な利用やライセンス供与が難しくなります。これにより、商業的な機会が失われる可能性があります。
信頼性の低下
著作権が帰属しない場合、自身の作品の信頼性や信用が低下し、他者との交渉や取引において不利になる場合があります。
著作権の帰属に関する取り決めや法的保護は、作品の価値向上や保護において重要な要素となります。したがって、著作権に関する取り決めは慎重に行うことが重要です。
システム開発の著作権に関連する様々なトラブル事例
ここまで、システム開発における著作権の帰属先やメリット・デメリットを解説しました。
しかし、著作権の帰属先を明確しないことで、どのようなトラブルが起こりうるか具体的に知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は実際に発生したシステム開発の著作権に関連するトラブル事例を紹介します。(※)
※出典:経済産業省「情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集」
トラベル発生の経緯
委託者はA社に対して珠算ソフトの開発を委託し、A社はそれを受託者に再委託しました。受託者は本件ソフトの開発を行い、A経由で委託者に納品しました。
その後、委託者は本件ソフトの販売を開始したものの、委託者からA社に委託料が支払われていないことから、受託者は本件ソフトの著作権を主張し、委託者に対して複製、頒布等の差止請求を行いました。
トラベルの争点
本件ソフトの著作権は誰に帰属するか、受託者と委託者の主張は以下のとおりです。
受託者の主張:
本件ソフトは、受託者がA社を介して委託者から再委託を受け、具体的な企画からプログラム作成までを行ったため、著作権は受託者にある。委託者の主張:
本件ソフトの基本的発想は、すべて委託者の提案によるものであるから、著作権は委託者にある。
判決
受託者の請求を認容しました。
委託者は本件ソフトを発注したに過ぎず、受託者が本件ソフトの企画設計及び制作を行ったため、本件ソフトの著作権は受託者に帰属する結論になりました。
また、委託者とA社との契約には、「本件システム中の成果物の所有権は、委託者よりA社へ委託料が完済された時に、A社から委託者へ移転する。ただし、成果物の中の、同種の成果物に共通に利用されるノウハウ、ルーチン、モジュール等に関する権利は、A社に留保される」との条項がありましたが、委託者が委託料を完済していない以上、権利は委託者に移転していません。
反省点
以下の2点が挙げられました。
著作権の帰属を契約に明記しておくべき
本件契約では、工業所有権に関する権利帰属は規定されてましたが、著作権の帰属は規定が不十分であり、委託者とA社、受託者との間に明確な合意がありませんでした。 そのため、今後の紛争を避けるためには、著作権の帰属に明確な規定を含めるべきだと判断しました。著作権を委託者に移転するつもりがあったとしても、所有権とは別に移転時期を明記しておくべき
委託契約では、委託料完済まで成果物の所有権がA社に留保されていましたが、判決では著作権も含めて権利は委託者に移転していないと判断されました。所有権と著作権は別個の権利であり、所有権の留保とは著作権の留保を意味しません。著作権に関しても委託料完済までの留保規定を明確にするべきでした。
システム開発における著作権に関する交渉例
著作権の帰属先を明確にすることが重要だと理解していても、具体的にどうやって交渉するか疑問を抱いている方もいらっしゃるでしょう。
システム開発を行う際、著作権の帰属先の交渉内容をいくつかパターンに分けて解説します。
契約交渉で行われること
開発者や開発会社とクライアントとの間で、契約を締結する際に、著作権の帰属に関する取り決めが行われます。
この際、開発者や企業が開発したシステムやソフトウェアの著作権がどちらに帰属するか、使用条件やライセンスに関して交渉が行われます。
共同開発での交渉
複数の開発者が協力してシステムを開発する場合、著作権の帰属と利用条件を明確にして合意する必要があります。
各開発者や企業との間で著作権の帰属先や利益分配、利用条件を交渉し、各々が納得できる形で交渉内容をまとめていきましょう。
取引先との交渉
開発したシステムやソフトウェアを取引先に販売する場合、その際の著作権の帰属や利用条件について、取引先と交渉が必要です。
この際、ライセンスの範囲や期間、使用条件、著作権の帰属先などに合意することが求められます。
ライセンス契約の交渉
開発したシステムやソフトウェアを他社にライセンス供与する場合、ライセンス契約における利用条件や著作権の帰属に関する交渉が行われます。
利用許諾条件、ライセンス料の取り決め、使用範囲、転売条件などの合意が求められます。
以上、著作権の交渉内容のパターンを解説しました。ここで解説した交渉内容は、著作権に関する重要な事項となるため、契約書や取り決めをしっかりと行い、また必要に応じて法律家や専門家の助言を求めることが重要です。
その際、著作権の帰属、利用条件、保護措置、訴訟解決などの様々な側面が十分に考慮される必要があります。
システム開発の権利を守るポイント
システム開発の権利を守るためのいくつかの重要なポイントを以下に示します。
- 契約の明確化
- 著作権登録
- 利用許諾契約の締結
- 技術的な保護手段の導入
- 相談窓口の設置
契約の明確化
開発者や開発会社とクライアントとの間で契約を締結する際には、著作権の帰属や利用条件、ライセンスに関する事項を明確に定めることが重要です。
契約書には著作権の帰属や使用条件、ライセンスに関する事項が明確に記載しましょう。
著作権登録
開発したシステムやソフトウェアに関連する著作権を登録することで、著作物の作成日時や権利者の情報が公に確認され、著作権を主張する際に有利となります。
利用許諾契約の締結
開発したシステムやソフトウェアを利用するユーザーや顧客との間で利用許諾契約を締結することが重要です。
利用許諾契約には、ライセンスの範囲、利用条件、権利者の権利や責務に関する事項が明確に定めましょう。
技術的な保護手段の導入
システムやソフトウェアには、技術的な保護手段を導入することが重要です。
著作権侵害や不正利用を防止するため、コピープロテクション、ライセンス管理システム、デジタル著作権管理(DRM)などの措置を検討してみましょう。
相談窓口の設置
開発者や開発会社内に、著作権に関する相談窓口や担当者を設置することで、内外からの問い合わせや相談に対応する体制を整えることが重要です。
これらのポイントを適切に考慮し、実行することによって、システム開発から生まれる著作物の権利を効果的に守ることができます。
まとめ
システム開発における著作権は、創造性やイノベーションを守り、知的財産権の価値を拡大し、法的保護と責任の明確化を実現する重要な要素です。
著作権の保護は、著作権登録や利用許諾契約の締結、技術的な保護手段の導入などによって実現されます。開発者や企業は、これらの手段を適切に活用し、自身の著作権を守り、事業の成長と競争力の強化を図ることが求められます。
「システム開発を外注したいけど、著作権の帰属先うまく交渉できるか不安」という方は、株式会社マイナビにご相談ください。予算や目的をヒアリングさせていただき、最適なご提案をさせていただきます。
著作権の扱い方やどのように開発を進めるかなど、気軽な質問だけでもかまいませんので、ぜひ当社にご相談ください。

Recommended Materials
おすすめ資料